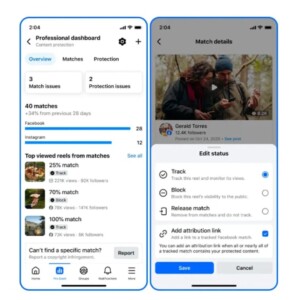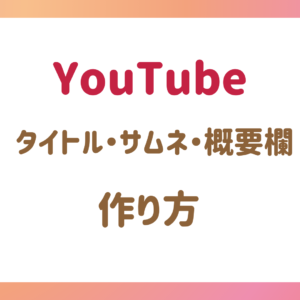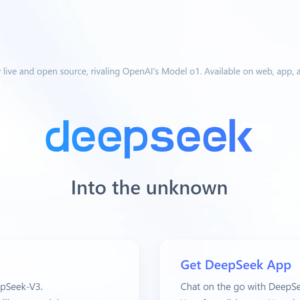SNS依存が招くリスク:SNSがいかに人に悪影響をもたらすかの論文一覧
目次
以下はSNSがいかに人間に悪影響をおよぼすかをまとめた論文です。
1. SNS利用とメンタルヘルスに関する研究
(1) Kross, E., et al. (2013).
タイトル: Facebook Use Predicts Declines in Subjective Well-Being in Young Adults
掲載誌: PLOS ONE, 8(8), e69841
概要:
- 目的: Facebookの利用が若年成人の主観的幸福感(Subjective Well-Being)にどのような影響を与えるかを検討。
- 方法: 被験者にスマートフォンを用いたアンケート調査を行い、Facebookの使用頻度と幸福感などを追跡。
- 結果: Facebookの使用頻度が高いほど、時間経過とともに主観的幸福感が低下する傾向が示唆された。
(2) Lin, L. Y., et al. (2016).
タイトル: Association Between Social Media Use and Depression Among U.S. Young Adults
掲載誌: Depression and Anxiety, 33(4), 323–331
概要:
- 目的: SNS利用と若年成人(アメリカ人)のうつ症状との関連を大規模調査で検討。
- 結果: SNSを頻繁に利用する層ではうつ傾向や不安傾向が高まる可能性が示唆された。
(3) Shensa, A., et al. (2017).
タイトル: Problematic Social Media Use and Depressive Symptoms Among U.S. Young Adults: A Nationally Representative Study
掲載誌: Social Science & Medicine, 182, 150–157
概要:
- 目的: 全米規模の若年成人を対象に「問題的なSNS利用(problematic social media use)」とうつ症状の関連を調査。
- 結論: 過度のSNS利用(自制が効かない利用など)は、うつ症状のリスクを高める可能性がある。
(4) Royal Society for Public Health (RSPH). (2017).
タイトル: #StatusofMind: Social media and young people’s mental health and wellbeing
概要:
- 内容: イギリスにおけるSNS利用が若者のメンタルヘルスに与える影響を調査したレポート。
- 結論: SNSは一部ポジティブな側面もあるが、InstagramやSnapchatなどの視覚中心のプラットフォームは、若者の自己肯定感を低下させ、孤立感や不安を増幅させる要因になりうると指摘している。
2. SNS利用と自己肯定感・ボディイメージへの影響
(1) Fardouly, J. & Vartanian, L. R. (2016).
タイトル: Social media and body image concerns: Current research and future directions
掲載誌: Current Opinion in Psychology, 9, 1–5
概要:
- 内容: SNS上での写真比較や“いいね”数の競争により、特に女性のボディイメージが損なわれやすいことを指摘。
- 結論: SNS利用は身体不満や摂食障害のリスクと関連する場合がある。
(2) Holland, G. & Tiggemann, M. (2016).
タイトル: A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and disordered eating outcomes
掲載誌: Body Image, 17, 100–110
概要:
- 目的: SNSが身体イメージや摂食障害のリスクに与える影響を体系的にレビュー。
- 結論: SNS上での美的基準(スリムさや筋肉質など)の理想化が、不健康な減量行動や過剰な美容整形願望に結びつく可能性がある。
3. SNS利用と孤独感・不安感
(1) Primack, B. A., et al. (2017).
タイトル: Social Media Use and Perceived Social Isolation Among Young Adults in the U.S.
掲載誌: American Journal of Preventive Medicine, 53(1), 1–8
概要:
- 目的: SNS利用の程度が社会的孤立感(Perceived Social Isolation)に与える影響を調べた。
- 結論: SNS利用が多いほど、実際には「孤独感」や「孤立感」を感じる度合いが高まる可能性がある。
(2) Savci, M. & Aysan, F. (2017).
タイトル: Technological addictions and social connectedness: Predictor effect of Internet addiction, social media addiction, digital game addiction, and smartphone addiction on social connectedness
掲載誌: Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30(3), 202–216
概要:
- 内容: SNS依存やスマホ依存が進むと、実生活での「つながり感」がかえって損なわれる懸念を提示。
- 結論: SNS利用は、人間関係の充実度よりもストレス増加や孤独感と関連する可能性がある。
4. SNSと学業成績・知的パフォーマンスへの悪影響
(1) Junco, R. (2012).
タイトル: Too much face and not enough books: The relationship between multiple indices of Facebook use and academic performance
掲載誌: Computers in Human Behavior, 28(1), 187–198
概要:
- 内容: Facebookでのチャットやゲームなどの利用時間と学業成績の関係を大規模に調査。
- 結論: Facebook上での雑多な活動に時間を費やす学生ほど、GPAをはじめとする学業成績が低い傾向が見られた。
(2) Kirschner, P. A. & Karpinski, A. C. (2010).
タイトル: Facebook and academic performance
掲載誌: Computers in Human Behavior, 26(6), 1237–1245
概要:
- 内容: SNS利用と学習効率の関連を研究。
- 結果: Facebookを利用する学生は、利用しない学生に比べて勉強時間が短くなり、学業成績が下がる可能性があると報告。
5. SNS利用と“FOMO”(見逃すことへの恐怖)
(1) Przybylski, A. K., et al. (2013).
タイトル: Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out
掲載誌: Computers in Human Behavior, 29(4), 1841–1848
概要:
- 内容: “FOMO(Fear of Missing Out)”がSNS利用者に与える影響を分析。
- 結論: FOMOが強い人ほどSNSへの依存度が高く、精神的ストレスや不安が高まりやすい。
(2) Abel, J. P., et al. (2016).
タイトル: The Extended Facebook Self: The Impact of Facebook on Offline Interactions
掲載誌: Computers in Human Behavior, 27(6), 6–14
概要:
- 内容: SNS上で他人の投稿を見逃したくない、常に最新情報を追わなければならないという心理(FOMO)が、オフラインでの人間関係にもネガティブな影響を及ぼすことを指摘。
6. 日本国内の研究・論文・調査レポート
(1) 日本小児科医会などの調査 (2019年頃~)
概要:
- 小児科医会などが実施した調査で、SNS上のいじめや誹謗中傷を含むトラブル増加を指摘。
- 特に中高生におけるSNS利用に伴う睡眠障害や学業不振の報告が増えている。
(2) 厚生労働省 研究班レポート (SNSトラブル関連)
- 近年、厚生労働省がSNSを活用したいじめ防止や自殺対策を行う一方、SNSでの誹謗中傷が社会問題化している点にも注目が集まっている。
- 青少年のネットリテラシー教育の推進が急務とされる。
(3) サイバーエージェント等による利用実態調査
- スマホの普及率とSNS利用の関連にフォーカスしたものが多く、長時間利用による健康リスクや対面コミュニケーションの不足、睡眠不足などを指摘している。
7. その他注目すべき書籍・文献
- Jean M. Twenge (2017).iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood.
- スマートフォンやSNSの普及が、Z世代(iGen)のメンタルヘルスや社会的行動にどんな影響を及ぼしているかを統計データを元に分析した書籍。
- Sherry Turkle (2011).Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other.
- SNSなどのテクノロジーが人間関係を変容させ、孤独感をむしろ増幅する点を論じた本。
- Cal Newport (2019).Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World.
- SNSの過剰な利用を見直すことで、より豊かな生活が送れると主張。SNSとの距離感について具体的な提案がなされている。
まとめ
- メンタル面への悪影響: SNS利用はうつや不安のリスクを高め、特に若年層の幸福感や自己肯定感を下げる可能性が多くの研究で示されています。
- 身体イメージへの影響: SNS上の完璧な容姿に対する比較意識が、ボディイメージの低下や摂食障害のリスク増加につながる場合があります。
- 孤独感・FOMO: SNS利用はつながりを増やすように見えて、実は孤独感の増大やFOMO(見逃すことへの恐怖)の発生を引き起こし、さらに依存度を高める悪循環が起きうると指摘されています。
- 学業・仕事の効率低下: 長時間SNSを利用する人は、学業成績の低下や仕事効率の悪化が報告されるケースが多く見られます。
- 日本国内の動向: 若年層のネット利用トラブルや誹謗中傷は深刻化しており、SNSリテラシー教育の必要性も強く訴えられています。
SNSは便利で楽しい反面、心理的負担やトラブルが増えるリスクも大きいと、多くの研究で示されています。こうした悪影響を理解しつつ、自分の利用時間や使い方を意識することで、ネガティブな側面を最小限に抑えることが重要です。参考文献や論文をぜひチェックして、SNSとの付き合い方を改めて考えてみてくださいね。